東北地方太平洋沖地震について23 (社協職員派遣の報告17)
- 2011.08.05
- 災害
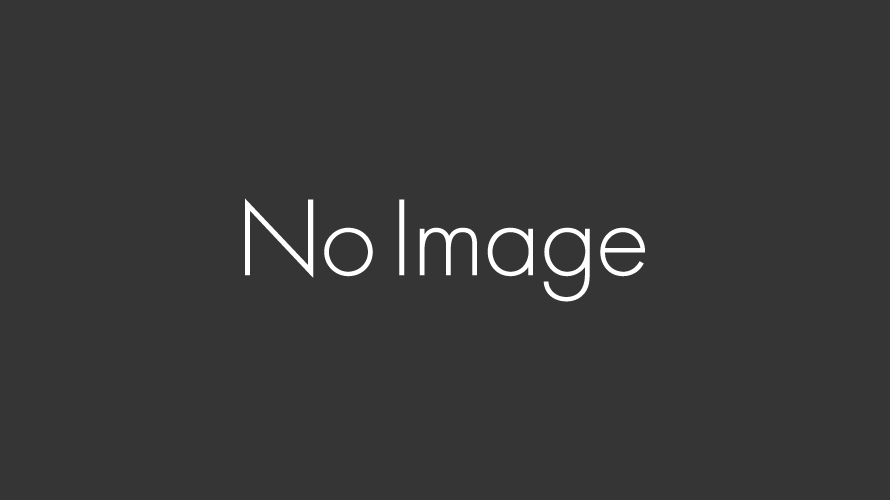

私は、7月21日から28日まで、岩手県山田町へ被災地支援に行ってきました。
山田町の現状は、津波で被害のあった木造の家は、土台以外が片付けられ、
鉄骨やコンクリートの建物はそのまま津波や火事の被害にあったままの形で残されているものがほとんどでした。
今でも、山田町で飲食店は道の駅だけですが、プレハブのコンビニがオープンするなど、少しずつ生活しやすくなっていました。
私の参加したクールでは県内社協職員3名が山田町災害ボランティアセンターに配属され、主に災害ボランティアに訪れた方の受付やボランティアを調整するニーズ・マッチング、を行いました。
ボラセンの主な現地職員は災害後に全員緊急雇用で採用された人ですが、5か月経ち、センターの運営もかなりスムーズで、今でも毎日100人以上のボランティアさんが来て活動しています。 ニーズの内容は、敷地内のガレキ撤去・避難所から仮設への引っ越し手伝い・イベントの補助(子供の遊び相手や調理の手伝い)・市からの物資配布などです。
被災当初と、今では必要な支援やできる支援が変わっていき、社協もその時々で形を変えていく必要があります。特に、目に見えない地域の問題に社協は気づき住民と共に解決していかなくてはなりません。
現在は、ボランティアの受け入れ・派遣だけではなく、仮設住宅に住む人たちのコミュニティをつくるために、仮設住宅の集会所を調査したり、サロンを企画したり、日ごろの困りごとを聞く等、と被災して自分も仮設住宅から通っている山田町社協の職員も、形を変えながら社協にできることを実現させていました。
静岡県内社協は、宮古市と山田町社協への支援を行っているのですが、その社協の主体性を尊重したうえで、人で不足の補助や物資の補助、助言という形でサポートしています。
実際私が活動したのは、6日間だけだったので、職員との関係性が作れ、業務の流れがわかり率先して業務を進められたと思ったら、6日目。本当に役にたったのだろうか。という思いでいっぱいで帰ってきました。
自分にできなかったことは次の職員につなげ、また静岡市が災害に合った時には、この経験を職員全体で共有し活かしていきたいと思います。
経営企画課 平岡由梨
-
前の記事
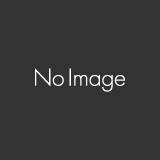
岩手県下閉伊郡山田町への物資支援「土嚢袋」をいただきました! 2011.08.04
-
次の記事
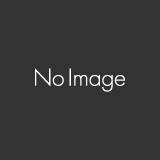
静岡ふれあい広場『当日ボランティア』大大大募集!! 2011.08.13